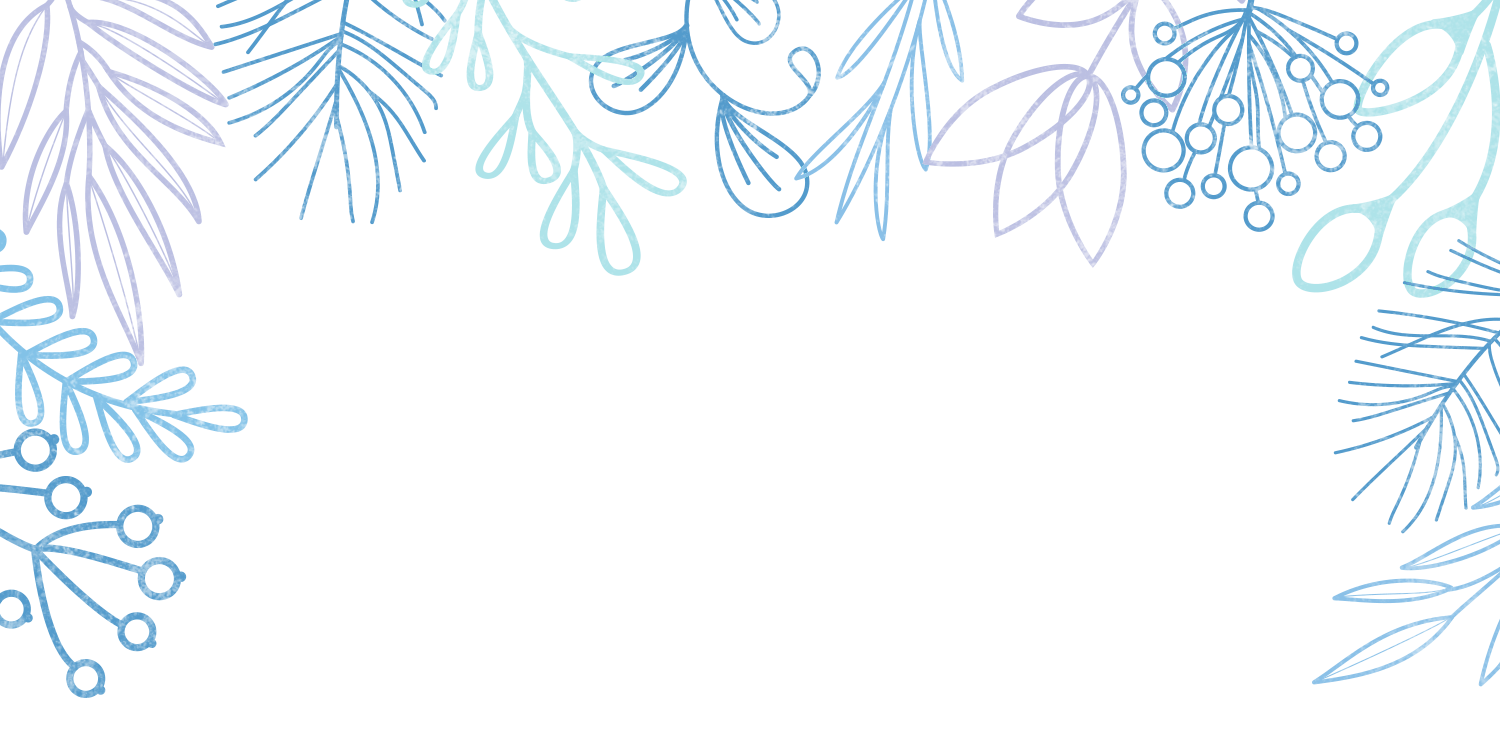プロフィール
こんにちは。接遇セラピー考案者の利光佳子です。
~言葉とふるまいで心を癒す~をコンセプトに、介護現場や対人援助場面での言葉や関わり方について研究しています。
正直に言えば、高校生の頃の私は、「福祉」や「ボランティア」に対してどこか冷めた見方をしていました。
「偽善っぽい」「嘘くさい」──そんな偏ったイメージを持っていたのです。
歳を重ねた祖母の歩く姿を見て「もっと早く歩けないのかな」と思っていたようなわたしが、いまこうして“接遇セラピー”を伝えている。人生とは、わからないものですね。
大学時代は就職への意識も薄く、「新聞記者になりたい」と軽く口にしたことがあったため、建前で新聞社を1社受け不採用。
卒業後のプランも曖昧で、妹のいる福岡で一緒に暮らそうかなと気楽に考えていました。そのような中で、アルバイト先の食堂の常連さんが「病院を紹介するよ」と声をかけてくださったのが、この道の始まりです。
紹介されたのは、大きな病院に併設された介護老人保健施設。介護や医療の知識も資格もなかったわたしは、見よう見まねで働き始めました。
認知症という言葉も、リハビリテーションという概念も、入職後に初めて知りました。
最初は生活支援相談員の補佐として働いていましたが、書類よりも現場に出て身体を動かす方が性に合っていて、現場異動を希望。
80名の入所者様を支える日々が始まりました。
この仕事は、やりがいと葛藤の両方を私に与えてくれました。
やりがいは、‟人間とは何か、老いとは何か、生きるとはどういうことか”という問いに日々触れられること。哲学的で、わたしの知的好奇心を強く刺激しました。誰かの役に立っているという実感も、大きな喜びでした。
一方で、葛藤もありました。
あるとき、困りごとを抱えた高齢者の話を丁寧に聴いていたわたしに、「業務の流れを妨げないで!」と強い口調で上司の指導が飛んできたのです。
「話を聴くことより、スケジュールをこなすことの方が大事なのか?」
そんな思いが心に残りました。
作業療法士の資格を取り、整形外科病院や老年期医療の現場でも働きましたが、「相手に丁寧に接したい」という気持ちと、「業務の効率を求められる現実」のはざまで揺れ続けました。
「みんな20単位とってるのに、あなたは16単位しかない」と指摘されるたび、自分のやり方が否定されているように感じ、悔しさが残りました。
それでも、心の奥にはいつも「わたしの大事にしたいケア」がありました。
管理的・威圧的な態度で高齢者に接する職員の姿に、心を痛めていた仲間もいた…
誰よりも、「相手に寄り添いたい」「丁寧に接したい」と願っていたのは、わたしたち自身だったと思います。
だからこそ私は、自分を裏切らないケアを実践できる環境を、自分で作る道を選びました。
“接遇セラピー”は、そのための方法です。
今、現場で葛藤しているあなたへ。
かつての私のように、「このままでいいのだろうか」と悩んでいるあなたへ。
この講座が、少しでもヒントや希望になればと願っています。