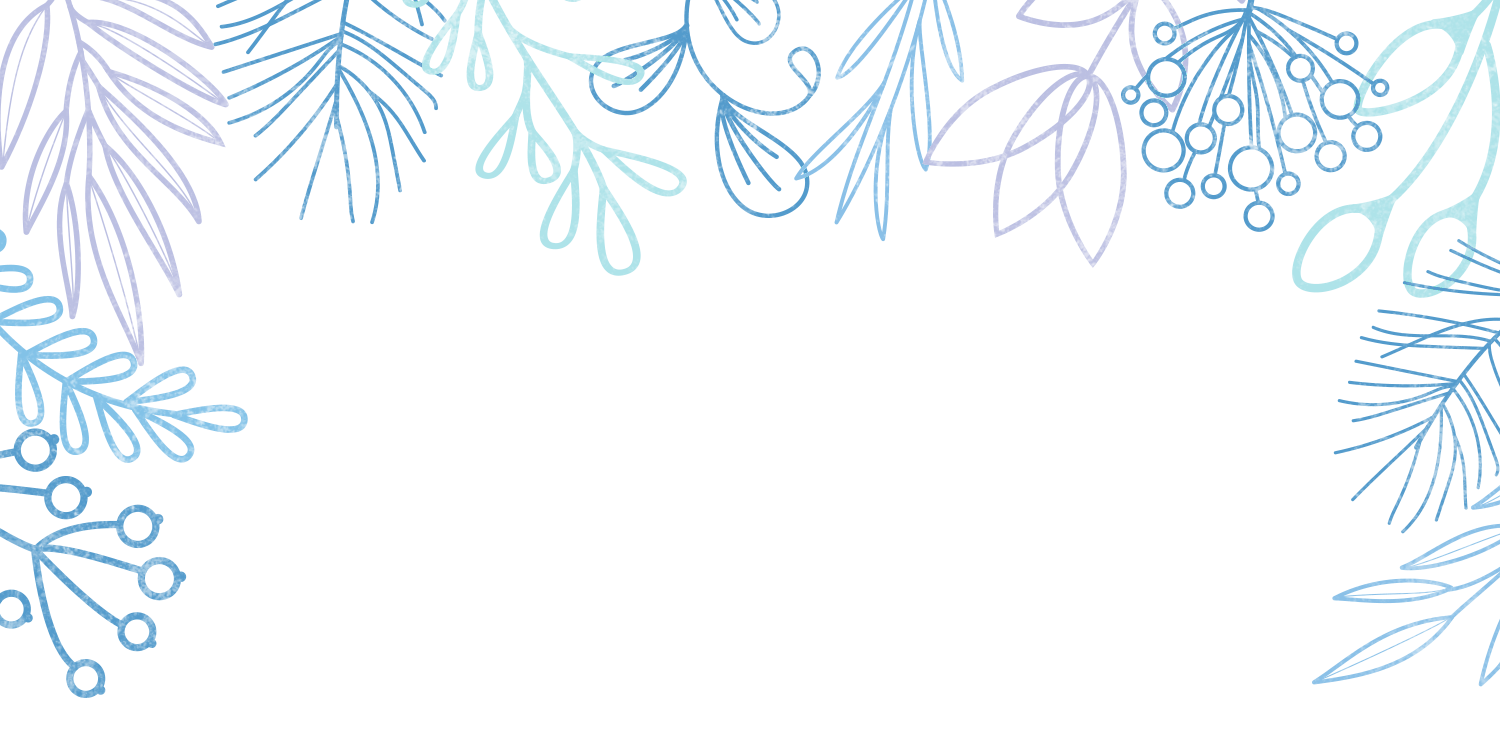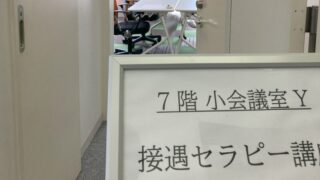優しさ大賞と、その裏の顔

介護や医療の現場で働いていると、
「接遇なんて理想論でしょ」
そう言いたくなるほど、日々は忙しく、心も体も疲弊しています。
それでもなお、不完全な自分を受け入れながら、誠実であろうと努めている。
この文章が、そんなあなたにそっと届けばと願っています。
わたしが初めて就職した介護老人保健施設では、月に1度、職員ミーティングが開かれていました。
正式な名称は思い出せませんが、その会の中で「やさしさ大賞」という表彰がありました。
職員同士で「この対応、優しいな」と感じた人の名前を紙に書き、
もっとも票を集めた人に賞状と副賞が贈られる仕組みです。
私はその1年間で、3度この賞をいただきました。
副賞の、やわらかい花柄のタオルが3枚、手元に残っています。
でも、心の奥にずっと、ある疑問が残っていました。
「私は、本当に“優しい”のだろうか?」
介護・医療の現場に22年携わってきました。
その中には、わたし自身の倫理的責任が問われても仕方ない、そう思う出来事もありました。
ここで書く方々は、すでに寿命を全うされました。
だからこそ、感謝と悔い、そして今の自分の原点として記させてください。
① 夜間のおむつ交換での出来事
90代の女性。背中が曲がり、全身の関節が強く拘縮していた方でした。
ある夜、おむつ交換のために伺った際、体に触れると突然、激しく腕をつねられました。
驚きと反射的な反応で、わたしも相手の腕をつねり返してしまいました。
② 体重測定での一幕
車椅子ごと乗れる鉄製の体重計に案内した際のこと。
90代半ばの男性に「こちらへどうぞ」と声をかけた瞬間、胸ぐらをつかまれました。
わたしはまた、とっさに胸ぐらをつかみ返してしまったのです。
近くにいた職員が駆け寄ってくれなければ、まるでプロ野球の乱闘のような場面になっていました。
③ 外出行事での行方不明
ある日、10名ほどのご利用者と神社に外出しました。
しばらくして、一人の女性の姿が見えなくなったのです。
周囲は木々と池に囲まれ、その先には交通量の多い国道。
警察に捜索を依頼し、最悪の事態も頭をよぎりました。
結果、その方は無事でした。神社から自宅まで、2.7kmの道のりを歩いて帰っていたのです。
ご家族によれば、かつてその道をよく散歩されていたそうです。
なぜ、こんなことを書くのか。
これを明かすことで、批判や非難を受ける可能性があることも承知しています。
それでも伝えたいのは、
わたし自身が今もなお、理想に向かって試行錯誤している途中にいる、ということ。
こうした体験があるからこそ、私は「接遇」について語る資格があると思っています。
「接遇なんて、現場でやってられない」
そう思う方にこそ、お伝えしたいのです。
小さな1歩から、一緒に始めませんか。
そして、あの行方不明になった女性や、ご家族、
いままで出会った人生の先輩方のおかげで、私は今もこの仕事を続けられています。
未熟なわたしを赦し、見守ってくれる存在があってこそ。
そのことを忘れないために、この文章を記しています。
身体的な接触だけでなく、
言葉や態度による虐待——
つまり、生きる意欲をそぐような関わり方、
または、利用者から職員が受けるハラスメント。
それらすべてが、この仕事には深く関わっています。
私が行っている講座では、こうしたテーマを「感情労働」という視点から見つめ直し、
「私は優しいのだろうか?」という問いに、丁寧に向き合っています。
もし、今この文章を読んでいるあなたが、
理想と現実の間で揺れているなら、
その気持ちを抱えたままでも、どうか一歩踏み出してください。
わたしも、その揺らぎの中で歩いています。