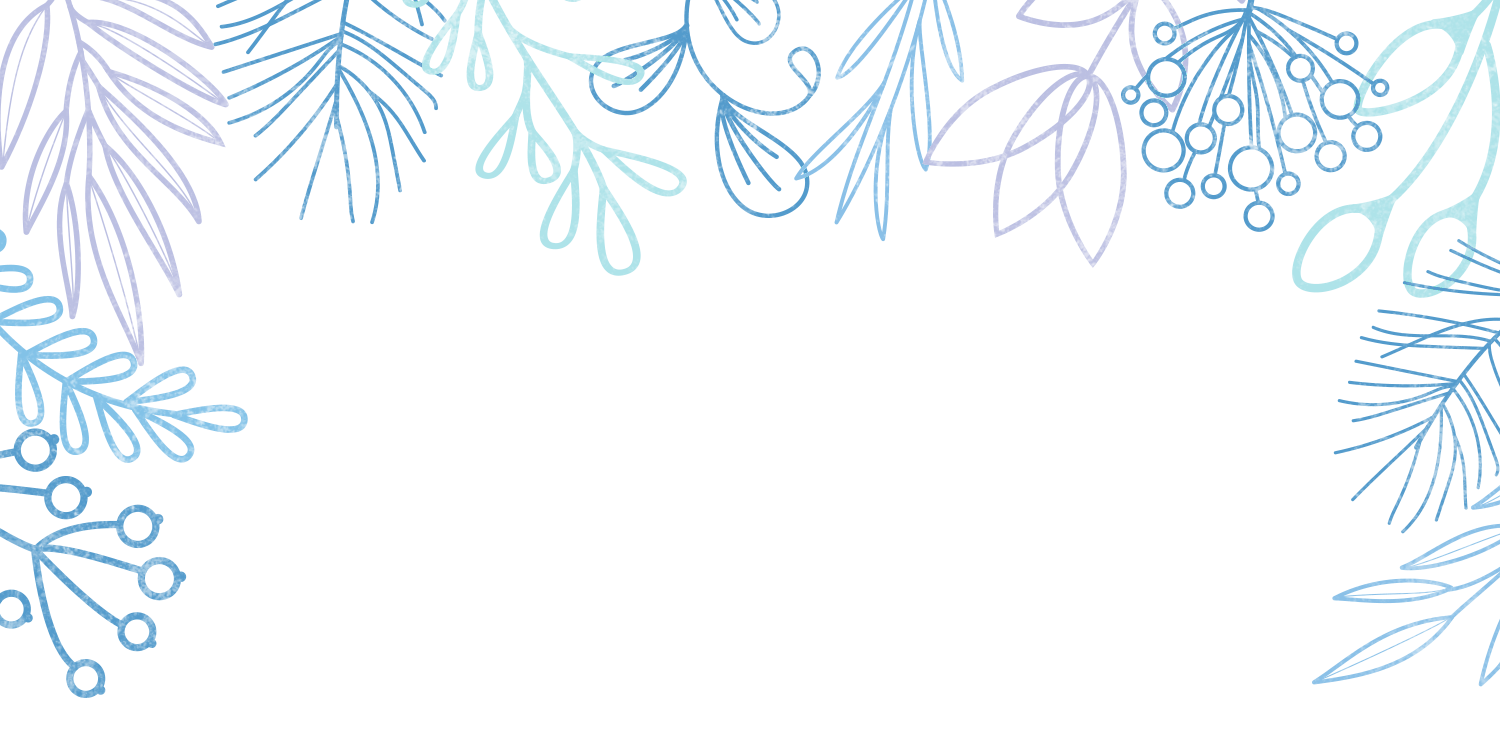接遇セラピー誕生秘話
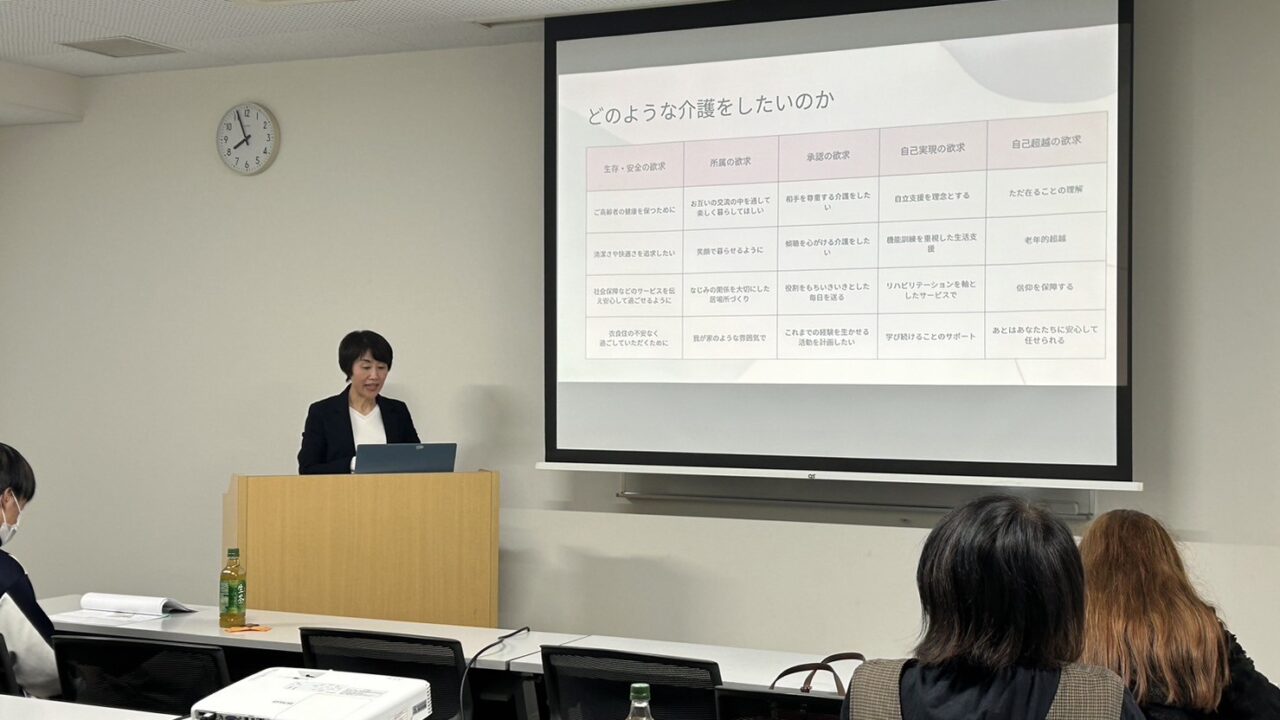
〜言葉とふるまいで、人の心を癒すということ〜
「接遇セラピー」という名前がふと頭に浮かんだのは、2023年の夏のこと。
それは、これまで学んできた2つのことがひとつに重なった瞬間でした。まるで、空からスーッと降りてきたような感覚。
ここでは、その“接遇セラピー”誕生の物語をお話しします。
【ひとつ目の学び】
電話応対企業研修 講師養成講座との出会い
2023年夏、日本コミュニケーション機構(JCO)代表・北平純子さんの「電話応対企業研修 講師養成講座」を受講しました。
もともと“応対”や“言葉づかい”には自信があり、それをもっと活かしたいと思ったのが受講のきっかけです。
振り返ると、私には電話応対に関する思い出がいくつもあります。
作業療法士の専門学校時代、住まいから遠く離れた実習先に段ボール5箱分の荷物を毎回送っていたのですが、お願いしていた地元の運送会社「大一急便」の社長さんから、ある日こう言われました。
「あなたの電話応対、すごくいいね。私の知る中でも5本の指に入るよ」
そして、就職が決まり鹿児島から宮崎へ引っ越す際には、なんと引っ越し代を無料でプレゼントしていただいたのです。
10年後、デイサービスで管理者をしていた頃も、「電話応対の印象が良くて、ここを選びました」と言われたことがありました。
また別の日には、結婚式の衣装合わせの際、お手洗いであいさつした女性が、後に全国的に有名な着付けの先生だと知り、「あなたの応対が素敵だったから」と、なんと1200万円の打掛を予算内で着せてくださったという出来事もありました。
思いやりのある応対は、相手の気持ちや行動を動かし、人生に思いがけないギフトをもたらしてくれる。
そして、それは介護の現場でも同じだと私は感じています。
対応ひとつで、高齢者の「生きる意欲」を支えることも、その逆もあるのです。
【ふたつ目の学び】
タイムマネジメント講座と“選択”の力
もうひとつのきっかけは、2022年11月に受講した「タイムマネジメント講座」。
講師は、タイムマネジメント研究家の篠原丈司さん。実は、夫の中学時代の同級生というご縁があり、気軽な気持ちで受講しました。
この講座の中で、「ゾウの寿命」の話が出てきました。
動物園で飼われているゾウと、野生のゾウ。どちらが長生きすると思いますか?
私は、手厚く管理されている動物園のゾウだと思っていました。ところが、正解は“野生のゾウ”だったのです。
この話が頭から離れず、後に調べたところ、その出典はシーナ・アイエンガー著『選択の科学』にありました。
この本の中で紹介されていたのが、老人ホームでの“選択”に関する研究。
入居者に「選べる」という自由度の大きい感覚を与えただけで、健康状態が改善し、死亡率が低下した。
つまり、たった一言の「声かけ」が、人の健康や寿命を左右する。
それを知ったとき、私はハッとしました。
介護の現場で毎日交わされる声かけこそが、利用者の人生に大きな影響を与えているのではないかと。
そして、これまで大切にしてきた「応対の力」と「選択を支える声かけ」が重なり、ひとつの形となったのが――
「接遇セラピー」でした。
【接遇セラピー講座のはじまり】
2023年11月、「接遇セラピー講座」の第1回目を開催しました。
最初は90分の単発講座としてスタート。受講してくださった皆さんが、実践の中で育ててくださったおかげで、今では少しずつ体系的にまとめられるようになりました。
受講される方の多くは、現場で長年、高齢者への“寄り添い”や“丁寧な関わり”を大切にしてこられた方々。
しかし、その一方で、周囲の荒い言葉づかいや、上からのような管理的な声かけに違和感を抱いている方も少なくありません。
「自分が大切にしてきたことは、間違っていなかった」
「やっと言語化してもらえた気がした」
そう語ってくださる受講生の声に、私自身も支えられています。
【これからの介護に必要な“癒しの接遇”とは】
接遇セラピーが目指すのは、「ことば」と「ふるまい」で相手の心を癒すこと。
でもそれは、相手のためだけではありません。
自分自身の心も、やさしく包みこむように癒されていく――そんな関わり方を、これからの介護の現場に広げていきたいのです。
誰よりも、自分自身が癒される介護を。
そして、利用者とともに“生きる喜び”をわかちあえるような、新しい接遇のあり方を、これからも伝えていきたいと思っています。