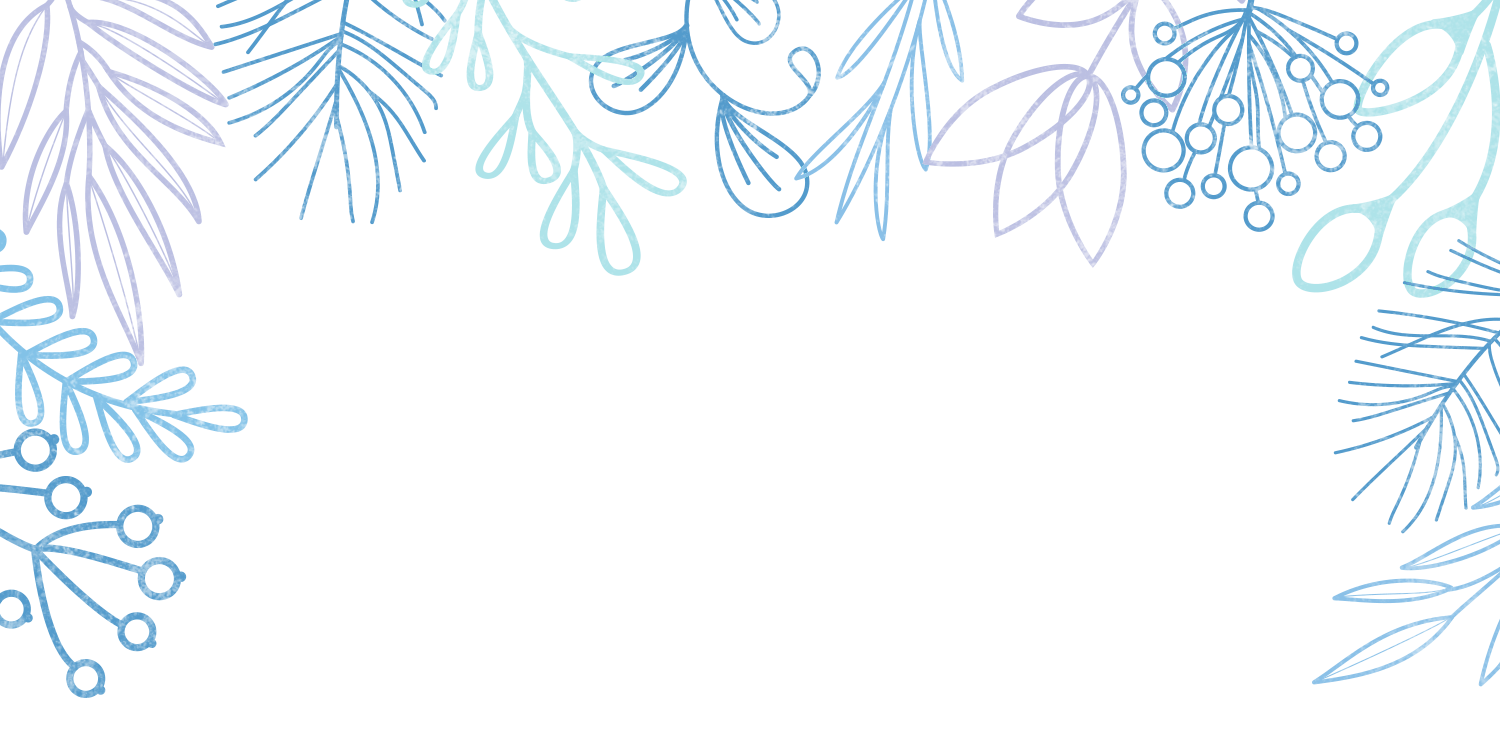声かけは基本。でも「どんな声かけ」かが、問われています。

介護の現場では、「声かけ」は支援の基本とされています。
確かに、言葉は安心感を与え、信頼関係を築くために欠かせないものです。
けれど日々の業務のなかで、こんな風に感じたことはありませんか?
「この声かけ、急がせるためだけになっていないか…」
「相手の気持ちを置き去りにしていないか…」
忙しさのなかで、ふと立ち止まると、
「言葉が、ケアの温度を決めている」と気づくことがあります。
声をかける、その前に考えたいこと
介助の際に発するひとこと。
それは、ただの作業のための指示ではなく、
目の前の人に「あなたを大切に思っています」と伝える機会にもなり得ます。
ですが反対に、その一言が
「急がせる」「従わせる」「自分で決める力を奪う」ことにつながってしまうことも。
言葉には、相手の尊厳を支える力も、削ぐ力もあるのです。
どんな声かけが「支援」になるのか?
■ 必要な声かけ
- 介助に対する同意や、希望を尋ねるとき
- ケアの内容や目的を説明するとき
- 戸惑いや不安が見えたとき
- 相手が迷っているとき
- 励ましや寄り添いの気持ちを届けたいとき
■ 不要な声かけ
- 相手が自分でできることへの過剰な声かけや指示
- 支援者側の段取りや効率のための一方的な言葉
- 自分の価値観ややり方を押しつける声かけ
- 相手を「管理するため」に使われる言葉
声かけの質が変わると、ケアの質も変わる
「声かけ」は、単なる手順の一部ではありません。
それは、目の前の人との関係を築く、もっとも身近なふるまいのひとつです。
意識的な言葉づかいが、
● 相手の心の安心に
● 自尊心の維持に
● そして「自分でできた」という力の実感に
つながっていきます。
あたたかな言葉が、支援になるように
介護の仕事は、技術だけではなく、
一人ひとりの存在を尊重しようとする気持ちがあってこそ、成り立つ営みです。
だからこそ、「声をかける」という、日々の小さなふるまいを
見直してみることは、大きな意味を持ちます。
忙しい現場だからこそ、言葉に心をのせる――
そんなケアができたとき、
きっと相手の表情も、自分の気持ちも、やわらかく変わっていくはずです。